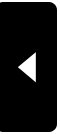2008年06月16日
吉竹遺跡 地元説明会
15日の午前中、牛倉地区において遺跡の地元説明会が行われました。第2東名高速道路建設に伴う発掘調査で、弥生時代後期から古墳時代前期頃の竪穴住居が5棟発見され、約1900年前から牛倉地区で人々が定住生活をしていたことがわかりました(説明会資料より)

元々は田んぼだった土地で遺跡が発見されたそうです。説明会の当日は朝から多くの地元住民が集まっていました。

皆さん、担当者の方の説明を熱心に聞き入っています。弥生時代の人々の暮らしに思いを馳せているのでしょうか!?自分たちの住む土地から、千年以上も昔の人々の暮らしが垣間見えるというのは何とも不思議な感じがします。

担当者の方の説明はとても丁寧でわかりやすいお話でした。説明会が終わった後も、住民の方の質問に個別に対応されていました。

竪穴住居の建物跡や「土杭」と呼ばれる穴を石灰の白線や看板で表示しています。現場で遺跡を見ながら説明を聞いていると、なんだか当時の暮らしぶりが見えてくるような気がします。

この吉竹遺跡では土器も出土しました。食器として使われていた「壺(つぼ)」「甕(かめ)」「高杯(たかつき)」といったものや、紡績車と呼ばれる糸をつむぐ道具や石包丁と思われる破片も出土しています。









 愛知県埋蔵文化財センターホームページ
愛知県埋蔵文化財センターホームページ
こども講座や考古学入門講座、県内の遺跡調査内容さまざまな遺物や調査風景の写真などが検索できます。
・吉竹遺跡 調査速報 その1
元々は田んぼだった土地で遺跡が発見されたそうです。説明会の当日は朝から多くの地元住民が集まっていました。
皆さん、担当者の方の説明を熱心に聞き入っています。弥生時代の人々の暮らしに思いを馳せているのでしょうか!?自分たちの住む土地から、千年以上も昔の人々の暮らしが垣間見えるというのは何とも不思議な感じがします。
担当者の方の説明はとても丁寧でわかりやすいお話でした。説明会が終わった後も、住民の方の質問に個別に対応されていました。
竪穴住居の建物跡や「土杭」と呼ばれる穴を石灰の白線や看板で表示しています。現場で遺跡を見ながら説明を聞いていると、なんだか当時の暮らしぶりが見えてくるような気がします。
この吉竹遺跡では土器も出土しました。食器として使われていた「壺(つぼ)」「甕(かめ)」「高杯(たかつき)」といったものや、紡績車と呼ばれる糸をつむぐ道具や石包丁と思われる破片も出土しています。
こども講座や考古学入門講座、県内の遺跡調査内容さまざまな遺物や調査風景の写真などが検索できます。
・吉竹遺跡 調査速報 その1
Posted by 藤本忍 at 21:22│Comments(0)
│新城市内の風景